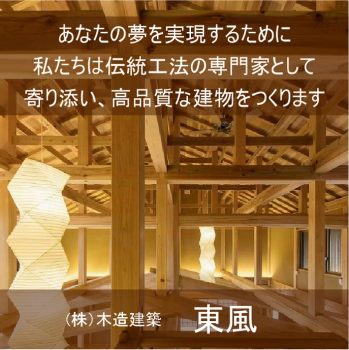誰でも判っている当たり前のことですが、人間は年をとります。
生きている限り、いつかはみんな子供から大人になり、おじいちゃん・おばあちゃんになって死んでいきます。
そんなことは判っているんですが、意外ときちんと認識していないのが、
『子供が中学生になると、自分が何歳になって、うちの親父はその時何歳なんだろう?』
『じゃあ、高校生になったら・・・?』
『下の子供が結婚する頃には自分たちは何歳になっているんだろう・・・?』
という、家族全員の具体的な年齢推移の把握です。
最近、東風である物件の設計の際にこの未来年表(←勝手に名付けました)を作ってみたんですが、一度こういう年表を作って家族の年齢の推移を可視化すると、将来のいろんな現象がいろいろ想定できるようになり、とても便利だなぁということに気付きました。
表自体は excel で簡単に作れるものですが、参考までにPDFファイルにしてみましたので、もし良かったら使って下さい。
こんな感じですね。
【追伸】
ふと思いついて、検索エンジンで未来年表と検索してみたところ、こんなサイトが見つかりました。
ちょっと覗いてみると「へぇ~」という情報がてんこ盛り。
なかなか面白そうです。
あなたはどちらが好きですか?
30年後に「そろそろ建て替えようか・・・」と言われる家と
「200年前のおじいちゃんが建てたの」と2210年に言ってもらえる家
東京スカイツリー
週末は日本民家再生協会の理事会に出席するため、東京へ行っていました。
今回往路は飛行機で行ったので、羽田から高速バスに乗っていると、隅田川越しに工事中の東京スカイツリーが見えました。
上の写真中、左から2本目の高い塔のようなものが東京スカイツリーです。
この東京スカイツリー、最終的には高さ634mになるそうですが、日頃2階建ての木造住宅に携わっていることが多い建築家としては、
「いったいどんな構造になっているんだろう・・・」
と興味が尽きません。
ちょっとだけ東京スカイツリーのサイトを覗いてみると、なかなか興味深いことがたくさん紹介されています。
ついついのめりこんで読んでしまうと業務が進まないので、ちょこちょことしか読んでませんが(笑)。
でも、工事中の現場見学とかあったら行ってみたいなぁ。
最先端の英知を結集して造っているんだろうなと思うと、ぜひその概要を知りたい衝動に駆られてきます。
(株)木造建築東風のサイトはこちら
世界に、300年先も美しい風景を
読んでます。等伯の本
今週になって身辺が少し落ち着いてきたので、久~しぶりに本を読み初めました。
昨年末から、新聞とか書籍とかの活字の類をほとんど読んでいない(というか読む時間が作れない)という状況が続いていました。
京都の現場も無事終わって、今は束の間現場が動いていない状態になっているので、スタッフも含めてちょっとホッとしている状態です。
今日は近くの瑞ヶ丘公園でお昼にみんなで花見をしました。
(伊丹は今ちょうど満開で、これから散っていくところです)
で読み始めたのが、桃山時代の絵師・長谷川等伯の半生を描いた『松林図屏風』。
読み物としてもとても面白く、ぐいぐい引き込まれていってます。
僕は長谷川等伯の絵が大好きで、明日から京都国立博物館で始まる等伯展で松林図屏風(国宝)を見るのが今から楽しみで仕方ありません。
空いている時にじっくり見られるといいなぁ。
(株)木造建築東風のサイトはこちら
世界に、300年先も美しい風景を
素晴らしい銘木を集めた旧・来住家住宅
昨日は、兵庫県西脇市にある旧・来住(きし)家住宅に行ってきました。
目的は、日本民家再生協会の近畿地区運営委員会に参加するためです。
いつもはこの地区運営委員会も大阪市内の会議室で会議を行っていますが、
「たまには遠出してちょっと楽しみながら会議をやろう」
とのことから、西脇市内でやることになったという次第です。
僕は西脇市へ行くのも初めてで、もちろん旧・来住(きし)家住宅も初めてだったのですが、この家は材料も仕事もすごかったです。
ちょっとご紹介しますね。
上の写真は離れの書院欄間の組子の写真です。
松葉継(まつばつぎ)模様というそうですが、こんな組子は初めて見ました。
(正直なところ個人的にはあまり好きではありませんが、仕事としてはものすごいと思います)
上の写真は母屋座敷の書院天板のケヤキです。
見事な玉杢(たまもく)が出ています。
この巾でこんな風に玉杢が出るということは、この木はきっとものすごい樹齢を重ねた太くて稀な木だったと思うのですが、よくこれだけの木を探してきたものですね。
原木の時の姿を見てみたいです。
この家では他にも春日杉や屋久杉、楓、桐、肥松、栂、黒檀、鉄刀木(たがやさん)、楠など様々な銘木がふんだんに使われて、とても丁寧な仕事が施されていました。
僕はもともと工務店で数奇屋建築の現場監督を務めていたので、銘木類を集めてきて建物の随所に使っていくという考え方には馴染みが深いのですが、今こういう建物を見ると正直ちょっと引いてしまいますね。
英知と財力を結集した、最高級の日本建築の一つであるということには間違いがないのですが、自分が目指す方向・建物を作っていく上で大切にしたいものとはちょっと違うなぁ・・・という違和感を感じます。
時代の流れなのか、それとも単なる好みの問題なのかはわかりませんが・・・。
しかし、久しぶりにすごい材料と出会えて感銘を受けました。
すみません、かなりマニアックな話題になってしまいました。
(株)木造建築東風のサイトはこちら
世界に、300年先も美しい風景を
地盤調査でビックリ!こんなこともあります
昨日は兵庫県明石市内で、Kさんのお住まいの計画のために地盤調査を行いました。
調査方法は、これまでにもブログで何回かご報告している、いつものスウェーデン式サウンディングです。
標準的には、1つの敷地内で5ポイントにわたって地中へ錐を打ち込み、その落下速度の速い/遅いによって地耐力(ちたいりょく=地盤の固さ)を測定します。
過去に行った近隣の地盤調査結果や周辺の地形・文献などから、おそらくそんなに弱い地盤ではないだろう、と予測していたのに、最初の測定ポイントで錐(きり)がスルスルと怖いぐらいに沈んでいきました。
錐がスルスルと沈む=地盤が弱い、ということを表します。
結局支持地盤に到達したのは、地表面から地中へ10m潜ったところでした。
「えぇ~、そんなに弱いの!?」
と、意表を突かれてちょっと不安&心配になりましたが、他のポイントで調査し始めると、当初の予想通り割としっかりした地盤であるという結果が出てきて、結局は一番最初に潜らせたポイントだけが、他と比べて異常に弱かった、という結果に。
こうなってくると、なぜそうなるのか不思議で仕方ありません。
ところが今回の計画地は、たまたまクライアントであるK様の奥様のご実家の隣だったのですが、お母様が助け舟を出して下さって事なきを得ました。
というのは、そのあたりには昔、大きな井戸があったとお母様が教えて下さったのです。
全体的な地盤の性状としては、このあたり一帯はさほど神経質になる必要が無いだろう、ということはあらかじめ予測していたのですが、この家の荷重の1/8程度が集中的にかかるこの1点(←出隅の通し柱の直下)に昔井戸があったせいで、たまたま局所的に非常に弱い地盤であるということは、地盤調査を実施していなかったら見逃していたことでしょう。
やはり地盤調査は欠かせませんね。
これから家づくりに臨まれる方は、必ず設計に先立って地盤調査をして下さい。
費用は3~5万円程度で済みますから。
感銘を受けた言葉
東風では建物の計画についてのご依頼を頂いた方へ、まず手始めにアンケート形式の要望書をご記入いただくことにしています。
これはA4用紙×4枚にわたる、家づくりに関連するいろんな事柄についてお尋ねするものです。
先日来新築計画についてご相談いただいているクライアントの方からつい最近頂いたご要望書の中に、とても感銘を受けた言葉がありました。
「あなたが今回の家づくりで大切にしたいと考えていることは何ですか?」
(複数回答可)
という質問に対する答えの一つとして、
「質素で心豊かに暮らせる家」
という回答を頂きました。
(T様すみません、無断でご紹介させていただきました)
この言葉を僕は移動中の電車の中で目にしたのですが、いや、なんとも素晴らしい言葉だなぁ・・・と感動し、しばしボーっとしてしまいました。
【何となく心の中で意識しているけれど言葉にできないこと】
というのは誰しも持っている感覚だと思うのですが、それをズバっと表現して頂いて、目の前が晴れ渡ったような感覚を覚えました。
T様、おかげでいろんなことを考えさせられました。
どうもありがとうございました。
感謝
桜情報@京都ほか
全国いろんなところで桜が咲き始めている(もう終わったところも)と思いますが、京都市内は今週末あたりがちょうど見頃だと思います。
下の写真は昨日左京区の疎水べりで撮った桜です。
この木は8分くらい花開いていました。
木によって開花状況は様々ですが、京都市内では今週末から来週の前半にかけて満開の桜が楽しめると思います。
例年東京が3-4日早く咲き始めて、その後を追うように関西でも咲き始めるのが常なのですが、今年は関東と関西とほぼ同時みたいな感じがします。
伊丹では京都よりもちょっと遅いかも。
これから京都へお出かけの方は参考にしてみて下さい。
今週火曜日に吉野へ行ってきたのですが、吉野も下の方は咲き始めていましたよ。
吉野での見ごろは来週末あたりかな、と思います。
もう1つ京都情報を。
例年、春と秋に一般公開されている京都市上京区の四君子苑ですが、先日友人から聞かれて問い合わせてみたところ、今年の春の公開は4/20-25だそうです。
興味のある方は足を運んでみられてはどうですか?
ちょうどそのころは、例年だと仁和寺の御室桜とか平安神宮のしだれ桜などが見頃です。
京都市N様邸竣工写真-2/伝統構法石場建て住宅
昨日に引き続き、京都市N邸内観の竣工写真をご紹介します。
↑ 玄関です。
ものすごくシンプルな玄関ですが、いろいろ苦労が詰まっています。
(話し始めると長~くなるので割愛しますが、過去のブログで
そのうちのいくつかはご紹介済みです)
↑ リビングの吹き抜けと薪ストーブです。
完成見学会の時には建具が入っていなかったのですが、無事土壁も乾いて建具が入りました。
↑ ダイニングカウンター越しにリビングの反対方向を見たところです。
このダイニングカウンターに使っている木は、クライアントのN様ご夫妻が2年前の伐採に立ち会われた、思い出深い木です。
ついでに言うと、テレビが載っているカウンターの1枚板や、玄関の式台に使われている1枚板も全て同じ1本の木から採りました。
原木で木を買うとこういうことができるんですよね。
↑ 最後はキッチンです。
このキッチンは大阪のステンレスキッチンメーカー/ルプさんの製作によるものです。
最近、このようにカウンターの下には引き出しなどを何も設けない、すっとんとんのキッチンを所望される方が増えています。
実はこれらの写真以外にも、もっといろいろとご紹介したい写真を山ほど撮っている(笑)のですが、このくらいにしておきます。
このお宅の家づくりの全容は木造建築 東風(こち)の以下のページでご覧になって頂けます
→ http://www.mokuzo-architect.jp/works_kyoto1.html
(株)木造建築東風のサイトはこちら
世界に、300年先も美しい風景を
京都市N様邸竣工写真-1/伝統構法石場建て住宅
京都市N邸では土壁もほとんど乾き、木製建具も入ってようやく建物は完成の姿になりました。
土日の2日間で作業の合間に竣工写真を撮ってきましたので、そのうちの何枚かをご紹介します。
※全ての画像はクリックすると拡大表示できます。
外観はこんな感じです。
外構がまだ一部仕上っていないので、足元をカットしているアングルで撮りました。
上の写真は玄関まわりです。玄関の建具は京都らしいシンプルな格子戸にしています。
この写真(↑)は南側の外観を横から撮ったカットです。
屋根には樋をつけていないので、造園を担当して下さった宮川庭園の宮川さんが古瓦を使って雨落ちを作ってくれました。
砂利が敷き詰められているところは、巾 60 cm × 深さ 30 cm ほどの排水溝になっていて、屋根からここに落ちた雨水は砂利の間を縫って公共下水に排水されるようになっています。
上の写真はリビング南面の窓を通じて、照明で照らされた内部の木組みを外から撮ったカットです。
昼間は外の方が明るいので、外からはガラスに反射して室内の木組みは全く見えませんが、夜になって室内の方が明るくなると、吹き抜けの木組みが外から丸見えになって、建物の表情が一変します。
設計した本人が言うのも何ですが、毎日この景色を見ながら家に帰ってくることができるのは、とっても羨ましいなぁ・・・と思います。
明日は内観の写真をご紹介しますのでお楽しみに。
(株)木造建築東風のサイトはこちら
世界に、300年先も美しい風景を