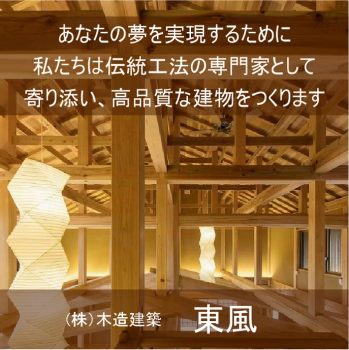これから少しずつ機会を見つけて、僕の目
から見た(←ちょっと変わってるかも・・・)
建築のご紹介をしていきたいと思います。
タイトルにもうたっているように、僕は木造
建築家ですから、木造建築のご紹介が多く
なると思いますが、それ以外のものも採り
上げていきます。基本的に自分が行って感
じたことをお伝えしたいと思っています。
まず最初は、イタリア・ベニスにある、
サンマルコ寺院の床のモザイクです。
床一面にこんなモザイクが施されています。
材料はすべて大理石ですが、その色の鮮や
かさ、取り合わせ方、形のユニークさ、加工技術など、ただただ見つ
めているだけでタメイキが出てきます。さすがイタリアだなぁ・・・と感じ
ました。大理石はやわらかいので、たくさんの人に踏まれるうちに少し
ずつすりへっていったようなのですが、石の種類によってすりへる具
合が違って、微妙にでこぼこした感じがまた何ともいい具合でした。
(株)木造建築東風のサイトはこちら
世界に、300年先も美しい風景を