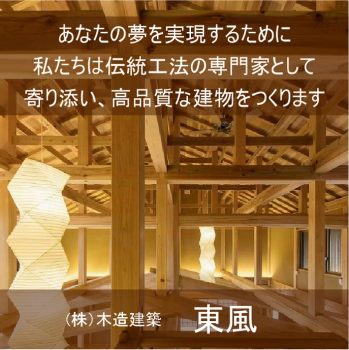京都市N邸では階段の手摺が取付きました。
実は先週のNさんご夫妻との打合せを行うまでは、玄関につける手摺を丸太で作ろうかと考えていたのですが、実際に丸太を現場に持ってきてやってみたら室内の雰囲気に合わなかったので、玄関の手摺は中止に・・・。
そこで階段の手摺を北山杉の小丸太にすることにしました。

北山杉の磨き丸太は自然の木の皮をむいて磨いたものなので、根元の方(1階の上り口)ではちょっと太目ですが、末口(2階の上がりきりの部分)では細くなっています。

上の写真は中間付近での手摺の拡大写真です。
ご覧のようにこの木は小さな入節が多いのですが、わざとこういう木を選びました。
和室の床柱などでもそうですが、つるっとした節の無い木は表情に乏しいので、象徴的な存在になる木の場合には、わざと小さな入節や筋(絞り)が入っているものを用います。
このような小さな入節はエクボと呼ばれて、床柱などでも割と好まれます。
人間と一緒で、床柱にエクボがあると微笑みかけているかのような愛嬌があってなかなかいいものです。
この材料は、いつも大変お世話になっている京都市上京区の中儀銘木店さんで買ってきました。

上の写真は、手摺の北山杉小丸太を受ける腕木(うでぎ)です。
ホゾの部分は柱に飲み込ませて鉛直方向の荷重を支えるように設計しています。
当初の設計では、手摺も杉の角材でつくり、手摺を支える腕木も既成の金物を使う予定でしたが、丸太が入って腕木も木製にすると雰囲気がかなり変わりました。
この腕木は赤松の柾目の古材から採ったものです。
とてもとても重い木だったので、きっと大工さんの刃物が刃こぼれしてしまったのではないかと思うのですが、とても丁寧に造り出してくれました。
このお宅の家づくりの全容は木造建築 東風(こち)の以下のページでご覧になって頂けます
→ http://www.mokuzo-architect.jp/works_kyoto1.html
(株)木造建築東風のサイトはこちら
世界に、300年先も美しい風景を