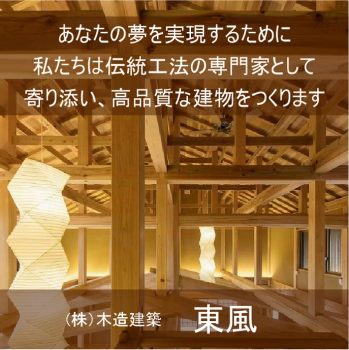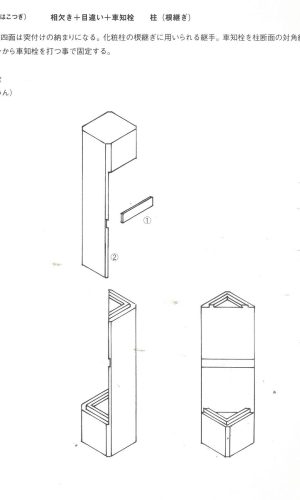2025年6月18日の午後に、東風のメールマガジン読者さま限定で、建築のコストと税額についての試算データをプレゼントしようと思っています。
これから作ろうと思っているのは以下の条件で比較したデータです。
土地の価格・建物の価格が同じだとすると、
新築と古い建物のリフォームで比べた場合、
税額を含めたトータルコストはどれだけ違うのか?
住宅を取得する際には、みなさまご予算の枠内でいろんな形での住宅を検討されると思います。
1.更地を取得して木造の新築住宅を建てるケース
2.築後30年以上経過した既存木造建物がある土地+建物を購入し、リフォームするケース
3.同じご予算で築30年のマンションを購入し、リフォームされるケース
4.同じご予算で新築のマンションを購入されるケース
これらのケースでは、【不動産物件取得金額 + 建築工事金額(新築・リフォーム代)】が同額だったとしても、その後かかってくる不動産取得税や固定資産税額がそれぞれ異なることはあまり認識されていません。
たとえば木造住宅は、税制上の法定耐用年数が22年とされています。
つまり22年経ったら税制上の評価額はゼロになりますよ、という意味です。
4000万円かけて新築した木造住宅よりも、4000万円かけてリフォームした木造住宅のほうが、固定資産税額はかなり安くなります。
その差額はいくらなのか?
鉄筋コンクリート造(RC造)のマンションの法定耐用年数は47年と定められています。
年々少しずつ減っていくとはいえ、木造よりも高い税率の固定資産税を47年間払いつづける必要があるということはあまり知られていません。
4000万円の新築マンションを購入した場合と、中古のマンション+リフォーム費用で合計4000万円の物件を取得した場合、固定資産税額を含めたトータルの負担額はどうなるのか?
差額はいくら?
つまり、物件に対して払うコストだけではなく、住み始めてからも考えてトータルで支払うコストがいくらになるのか?というところを試算&比較してみよう、というのが今回の企画の趣旨です。
この企画は(株)木造建築東風のメールマガジン読者さま向けの特別企画です。
もしこれについて知りたいと思われた方は2025年6月18日(木)お昼12:00までに東風のメールマガジンへご登録ください。
6/18の午後にメールマガジンを配信する予定です。
メールマガジンの登録は無料で、こちらからお申し込み頂けます。
ご興味のある方は、どうぞお忘れないように今すぐにご登録ください。